 |
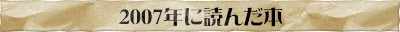
2007年6月に読んだ本のレビューです。
|
iPodは何を変えたのか?
THE PERFECT THING: How the iPod Shuffles Commerce, Calture and Coolness
スティーブン・レヴィ:著
上浦倫人:訳
ソフトバンク クリエイティブ:刊

|
2001年10月にアップルコンピュータ(当時。現在は社名から“コンピュータ”を取って単にアップル)が発表した1台の携帯ディジタルオーディオ(MP3)プレイヤーのiPod。
当時市場にはいくつかのディジタルオーディオプレイヤーが流通していたが、記憶媒体にメモリィを使用していたため収録曲数が少ないものや、どうしようもなく使いづらいものばかりだった。
iPodも、そもそも音楽の転送にMacintoshが必要であったり、5GBのハードディスクに1千曲収録出来ることを売りにしていたものの、コアな音楽ファンの膨大なCDライブラリィには対応しきれない、リモコンが付属していない、などのネガティブ要素もあったため、当初は一部のMacユーザーのオモチャに留まっていたが、その外観のクールさ、斬新なホウィールとシンプルなインターフェイスによる使い勝手の良さ、さらにコンピューター側の音楽ライブラリィ管理ソフトiTunes自身の使いやすさ、iPodとの連携の容易さなどが受け、ハードディスク容量のアップ、Windowsへの対応など着実に進化して行くに連れ爆発的とも言える勢いでユーザー層を広げていき、ついには携帯ディジタルオーディオプレイヤーのシェアナンバーワンの座を勝ち取ってしまう。
そんなiPodの魅力はどこに潜んでいるのか? iPodの登場は社会にどのような影響を与えたのか? に、《Newsweek》のテクノロジー担当記者であり、スティーヴ・ジョブズからの信頼も篤い著者が迫る。
* * * * *
《Newsweek》のテクノロジー担当記者で、『マッキントッシュ物語』(翻訳版の原書は絶版。復刊ドットコムから復刊されるも現在品切れ中)や、『暗号化』などの著作で知られる著者が、近年希にみる大ヒット商品となったiPodについて熱く語っています。
著者の視点はタイトルが示しているように、アップル(スティーブ・ジョブズ)が、iPod+iTunes──自分の音楽コレクション全てをデジタル化して持ち歩く──というソリューションを提供したことで、ユーザーの音楽体験や音楽業界の体質に、iPod以前とそれ以降でどれだけの革新をもたらしたか? という文化的側面を伝えることや、『マッキントッシュ物語』や『暗号化』がそうであったように、この世界における隠れたパイオニア/イノヴェイター達に光を当て、その反骨精神を賞賛することにフォーカスされており、ジョブズの時として妄執とも言える、品質向上を追求する姿勢や、自らの信念を貫く際に発揮するリーダーシップなどに触れてはいるし、ジョナサン・アイブなど、iPod開発のキィパースンへのインタヴュウなどはあるものの、開発ストーリィ自体は控えめなので、Macファンのためのネタ(トリヴィア)拾い本としては正直食い足りません(まぁ、どう聞いても近場のアルバムからピックしているようにしか感じられないiPodのシャッフルが、数学的には実は全くの「ランダム」である、というのはオドロキでしたが)。
だからといってつまらないわけでは決してなく、ウォークマンから始まるポータブルオーディオプレイヤーの歴史をおさらいしつつ、なまじ自分の音楽ライブラリを持ち歩くことが出来るゆえに、時としてiPodのプレイリストが所有者の趣味嗜好を暴露(笑)してしまうために起こる弊害(はるまきのプレイリストなんか、自慢できないリストの筆頭だからなぁ(^_^;))や、ポッドキャストのムーブメントがもたらす(かもしれない)市民メディアの台頭など、iPodが、単に「ディジタルオーディオプレイヤーとして大成功を収めた」という枠を越え、社会にどのようなインパクトを与えつつあるのか? といった「iPodの今」を綴った本としては良くまとまっていると思います。
|
|
すべては死にゆく
ALL THE FLOWERS ARE DYING
ローレンス・ブロック:著
田口俊樹:訳
二見書房:刊

|
ヴァージニア州にあるグリーンズヴィル刑務所で一人の死刑囚が刑の執行の日を待っていた。その死刑囚プレストン・アップルホワイトは、3人の少年を誘拐し、性的暴行を加えた上で殺した科で捕らえられていたのだが、本人は一貫して無実を主張していた。
そんなアップルホワイトに、アーン・ボディンスンと名乗る心理学者が、アップルホワイトが無実であることを信じていると称して近づき、言葉巧みにアップルホワイトに取り入って彼の信頼を得ていくが、実はそんなボディンスンこそが少年達を殺した張本人であり、4年前にスカダーに追いつめられニューヨークを去った殺人鬼だった。
一方スカダーは、AAの集会で知り合ったOLのルイーズから、出会い系サイトで知り合って付き合うようになった男のことに好意を持っているものの、あまりにも秘密めいたところがあり、このまま付き合って大丈夫なのだろうかという不安を覚えるようになったので、気持ちに踏ん切りを付けるためにもその男のことを調べて欲しいという依頼を受ける…。
* * * * *
アル中探偵<スカダー シリーズ>の第16弾で、前作で棚上げになった快楽殺人犯との決着が付く、事実上『死への祈り』の後編となっています。
シリーズ史上最も後味が悪いというか尻切れトンボな結末だった前作において、まんまと逃げおおせた“彼”が9.11後のニューヨークに舞い戻ってスカダーを狙う、というプロットはさすがにサスペンスフルですし、ついにスカダーが真相に辿り着くくだりなどはなかなか読ませるものがあるのですが、いかんせん、ミステリィ界でも屈指の邪悪さと狡猾を併せ持つと思われる、殺人そのものが目的と化した“彼”の思考形態・犯行の悪趣味さに辟易としてしまい、前半は読むのが辛くてしょうがありませんでした。
まぁ、サイコサスペンス、あるいはホラーとして読む分にはこういうのもアリだとは思うんですが、やはりこのシリーズに期待しているテイストというかイメージというかとの乖離に、個人的には付いていけなかったというのが正直なところです。
とは言え、作中でスカダー自身がしきりに老いについて口にすること、総棚ざらえと言わんばかりに、これまでに登場した人物やエピソードへの言及が多いことなど、訳者もあとがきで懸念しているように、ブロックがシリーズになんらかの区切りを付けようとしているかに見える本作、シリーズのファンなら“彼”との決着を見るというだけでなく、目を通しておいた方が良いエピソードかも知れません。
|
|
月下の狙撃者
THE DEVIL'S BED
ウィリアム・K・クルーガー:著
野口百合子:訳
文藝春秋:刊

|
アメリカ大統領夫人ケイト・ディクソンの父親のトム・ジョーゲンソンが、日課のようにしている月見をするため、トラクターで自宅の果樹園<ワイルド・ウッド>内の散策中、木の枝で頭を打って昏倒し、意識不明の重体に陥ってしまう。
シークレット・サーヴィスの特別捜査官ボー・トーセンは、ケイトが父親の見舞いのため<ワイルド・ウッド>に滞在することから、現場担当者として<ワイルド・ウッド>に配属されることになる。
シークレット・サーヴィスの直接の任務は大統領夫人の警護だが、事故現場を検分したトーセンは、トムが発見された際、トラクターのエンジンが切られていたことを突き止め警戒感を募らせるが、現場で指揮を執るクリス・マニングは、かつてトーセンとの間に生まれた確執から、彼の進言をまともに取り合おうとしなかった。
しかし実際に、自らを“ナイトメア”と呼び、<ワイルド・ウッド>のケイトを監視する不気味な影が潜んでいた…。
* * * * *
ファーストレディを付け狙う、復讐に取り憑かれた狡猾な暗殺者“ナイトメア”と、シークレットサービスの護衛官トーセンの対決が描かれる前半は、『ボーン・コレクター』の大ヒット以来のトレンドともなった、周到な準備によって捜査当局の裏の裏の裏をかく犯罪者対主人公という図式が採用されているので、後半もその線でトーセンと“ナイトメア”の第2ラウンドが繰り広げられるのかと思いきや、なんと後半はラドラムチックな(最近じゃ『24』ばりと言った方が通りが良いかな?)秘密結社の陰謀にトーセンが巻き込まれるという、「一粒で二度おいしい」アクロバティックな展開が読者を引っ張り、分量を感じさせない、なかなかのリーダビリティを発揮したミステリィとなっています。
惜しむらくは、“ナイトメア”のおぞましい出自があまりにもエキセントリックで絵空事っぽすぎるのと、「一粒で二度おいしい」展開とは言ったものの、故に前半と後半でタッチがガラリと変わってしまい、プロットの軸がブレているように感じさせてしまったり、トーセンとマニングの確執の描写も中途半端で「設定上の都合」感が匂ってしまう、など、端々でこなれて無い面が気になるのも確かで、この辺がもうちょっと練られていれば、星4つクラスの作品になったと思います。
|
|
殺しの標的
LINE OF FIRE
ドナルド・ハミルトン:著
鎌田三平:訳
東京創元社:刊

|
銃砲店を営むポール・ニキストは、ひょんなことから奇妙な友情関係を築くことになったギャングのボス、カール・ガンダーマンからの依頼で、州知事マーティン・メラニーの狙撃を実行するが、メラニーが予期せぬ動きをしたため狙撃に失敗してしまった上、たまたま隣のオフィスに顔を出したOLのバーバラ・ウォリスに銃声を聞き咎められてしまう。
ニキストは、バーバラの口を封じようと銃を抜いた、ガンダーマンが派遣したお目付役のチンピラを咄嗟に射殺し、彼女に目撃したことを黙っていた方が身のためであることを言い含め、狙撃に使ったライフルを預けて彼女を逃がしたため、ガンダーマンの計画は暗礁に乗り上げてしまう…。
* * * * *
<マット・ヘルム シリーズ>が有名(といってもはるまきは未読ですが(^_^;))なドナルド・ハミルトンの、ハードボイルドタッチが魅力的なガンアクション小説です。
「暗殺(ではないのですが)を目撃した女性を、騎士道精神から事件に巻き込まないよう主人公が奔走するうちに特別な感情が芽生え始める」というプロットや、狩猟中の事故がもとで不能になってしまったことで周囲に壁を作っている、心に傷を抱えた主人公像などは定番と言えば定番ですが、豊富な銃器に対する知識に裏打ちされたキレの良いアクションシーンや、ギャングのボスとの危うい友情──というよりは共生関係──の成り行きに対するスリリングさ、「妻は夫に不利な証言が出来ない」という法律(今はそんなことないんでしょうが)を利用し、バーバラと結婚することで彼女を守ろうとする破天荒なアイディアなど、随所に読ませどころがあります。
自衛の手段として銃器に全幅の信頼を置くメンタリティは、さすがに今の目から見るとやはり時代錯誤な感じが否めませんし、主人公の狩猟に対する偏屈とさえ言えるこだわりは、日本人の感覚からするとついていけない面もあったりはしますが、訳者が指摘しているように、どこか西部劇タッチを感じるハードボイルドとして、最後までテンポ良く読むことが出来る佳作に仕上がっています。
|
|
シリウス・ファイル
THE SIRIUS CROSSING
ジョン・クリード:著
鎌田三平:訳
新潮社:刊

|
MI5やMI6ですら嫌がるような汚れ仕事を請け負う首相直属のイギリスの秘密機関MRUに所属するジャック・バレンタインは、MRUのボスのサマヴィルに呼び出され、1972年にアイルランドにパラシュート降下したが、任務を果たすことなく死んでしまった工作員の遺体から書類を回収するよう命じられる。
一方で、属する組織こそ敵対しているが、古くからの友情で結ばれたIRAの伝説的な闘士リーアム・メロウズが突如バレンタインのもとを訪れ、リーアムがイギリス警視庁公安部の警部と取引をしていることを匂わせる捏造写真がもとで組織から追われていることを打ち明け、ジャックに手助けを求めてきた。
その途端、リーアムの追っ手から狙われたジャックは、任務を果たしつつリーアムに手を貸すべく、家代わりにしているトロール船<キャッスル・ドーン>でアイルランドに向かうが…。
* * * * *
2002年に新設された、CWA賞の最優秀スパイ・冒険・スリラー賞(イアン・フレミング・スティール・ダガー賞)の第1回受賞作となった、著者のエンターテイメント・ジャンルへの転向処女作です。
“スパイ・冒険・スリラー”賞を受賞しただけあって、場合によっては大義よりも信義や友情を重んじる登場人物達や大自然の猛威に立ち向かう状況が出てくるなど、英国冒険小説の王道を行くような数々の仕掛けが今や懐かしい、ヒギンズやバグリイといった正統派英国冒険小説の系譜を受け継ぐ物語に、純文学畑出身ならではの詩的な文章表現が程よいスパイスとなっている、なかなか印象的な冒険小説に仕上がっています。
とは言え、実は主人公ジャックの人となりというか、行動様式の源がどこにあるのかといった、主人公が主人公たることの説得力に欠けていたり、謎解き面で、もうひとひねり欲しいという食い足らなさが残ったり、「グロックのリボルバー」や「弾薬帯をM16に装填した」「M16は支持架から発射するつくりになっている」などなど、意味不明な銃器関係の記述(訳は手練れの鎌田三平なので、著者の銃器に対する知識不足の問題でしょう)には閉口してしまうなどの難点が散見されますが、最近ではすっかり寂れてしまった古き良き冒険小説の香りを味わうには良い小説だと思います。
|
|
Last Modified 2007/8/10
|  |