 |
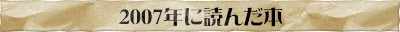
2007年1月に読んだ本のレビューです。
|
冬を怖れた女
IN THE MIDST OF DEATH
ローレンス・ブロック:著
田口俊樹:訳
二見書房:刊

|
スカダーは、ゆすりを理由に娼婦のポーシャ・カーから告訴されたニューヨーク市警の刑事ジェローム・ブロードフィールドに呼び出され、ポーシャの告訴はでっちあげで、市警内の腐敗を告発しようとする特別検察官に協力している自分が手を引くよう、誰かの差し金でポーシャは動いているに違いないから、自分を窮地に陥れた黒幕を捜し出して欲しいと頼む。
ブロードフィールドの立ち居振る舞いから、彼が話すことをまったく信用出来ず嫌悪感しか抱けなかったスカダーだが、事件の真相に興味を引かれたため依頼を引き受けることにする…。
* * * * *
アル中探偵<スカダー シリーズ>第2作です。
第1作の『過去からの弔鐘』の2ヶ月後に上梓されたのが直接の原因では無いのでしょうが、何となく練れてない感を感じるエピソードでした。
人格的にいささか問題があり、友達でも何でも無く、スカダー自身良い印象を持っていない依頼人とはいえ、無実の人間が罪を着せられたままであることを良しとしないという、他のハードボイルドヒーローとは毛色の違う公平さ(ノンポリとも言う?(^_^;))こそユニークだし、やれ正義がどうの真実がこうのといった大義を振りかざさない分、押しつけがましさが無いのは良いものの、ミステリィとしてはポーシャを殺した真犯人の動機に必然性が無いというか説得力に欠けて締まりがないし、真相を解明したスカダーが犯人に自らケリを付けるよう談判しに行くいう決着の付け方が『過去からの弔鐘』とカブるのも冴えず、アル中スカダーのダメダメぶりばかりが目立つ、シリーズ中でもあまり感心できないデキで、しかもそうなると、普段あまり気にならないスカダーの厭世的というか無関心な態度や、いわずものがなの反語を返す会話とかが妙に鼻についてしまうほどでした。
|
|
数学的にありえない (上) (下)
IMPROBABLE
アダム・ファウアー:著
矢口 誠:訳
文藝春秋:刊

|
たびたび起こる癲癇の発作を苦に教壇を下りた元統計学講師デイヴィッド・ケインは、持ち前のサヴァン的計算能力を活かし、ポーカーで日銭を稼ぐ生活に甘んじていた。
そんなケインは、癲癇の発作が起きる前兆の幻覚で気が散ったため、確率的に負けることなど無いと信じて強気に出た大勝負で負けてしまい、ナイトクラブに1万5千ドルもの借金を負ってしまう。
既存の治療薬では効果が無いケインは、このまま病気を放置して自分の将来が無くなることに危機感を覚え、かねてからかかりつけの医師から申し出を受けていた、医師が開発中の抗癲癇薬の被験者となることを決意する。
一方、NSAが収集した国内外の科学データを分析、有望な研究は政府機関に回したり、政府に協力的な民間企業にリークすることで国益に寄与してきた<科学技術研究所>の所長ジェイムズ・フォーサイスは、脳科学にまつわる興味深い実験データを発見し、その研究が有望だった場合、実験の被験者を奪うため、CIAに現場工作員を一人転属させてもらうよう要請する…。
* * * * *
「ダン・ブラウンに続く知的ミステリィの新鋭登場!」という呼び声も高い、第1回世界スリラー作家クラブ新人賞を受賞したアダム・ファウアーの処女作です。
確かに、叙述トリックを用いたどんでん返し(まぁ、少々小賢しくはありますが)や粋なラストなど、新人らしからぬ筆裁きを見せる部分もありますが、とにかく細部の詰めがおろそかなのがよろしくない。
例えば物語冒頭、北朝鮮に機密情報を売ろうとしたナヴァが、情報の収まったディスクに「まつ毛ほどの擦り傷」が付いて情報が読み出しが出来なくなったために窮地に陥るって設定なんか、「クラックならともかく、擦り傷くらいコンパウンドで磨きゃいいじゃん」とかツッコミたくなるし(しかも“レーザーディスク”って(笑))、北の諜報機関がシグやウージーといった西側の銃器を使ってるのも(潜入工作ならともかく)ウソ臭い。
このような、大風呂敷を広げるからこそ大事な、ウソを繕うほころびが最初に目についてしまうと、投薬を含む脳科学的な実験を大学の教授が実験室一人で行うなどという「科学的にありえない」描写には目をつぶるとしても、6メートルもの火炎の数メートル上のハシゴを、ナヴァが何の装備もないまま渡ってしまうとか、脚が180度曲がって膝の皿が砕けたケインが、ナヴァの応急手当てですぐびっこで歩けるなんてジェリー・ブラッカイマー印の映画ばりの「ありえなさ」や、「パソコンのシステムハードウェアにアクセスしてアプリケーションを開いた」(アプリがROMにでも焼かれてるのか?)とか、「拳銃や弾薬について、知ってちゃいけないようなことまで知っている」友人に協力してもらった割には、「拳銃(シグ ザウエル)の引き金を引いたがカチッという乾いた音が響いただけ」(スライドストップが壊れでもしてたか?)などという、散見されるITや銃器に関するお粗末な描写(さらに翻訳上も「ウージ」と「ウジ」って問題外の表記の揺れがあったり)が次々に気になってしまい、結局「前代未聞のアイデアを仕込んだジェットコースター」に乗りそこなってしまいました。
それでもノリノリの頃のラドラムの諸作や『24』のように、多少辻褄が合わなくても、有無を言わさぬテンションや構成の妙で受け手をだまくらかしてくれれば受け手も気持ちよくホラ話にノレるものですが、そういった文章的なパワーやテクニックも無い上、得意分野である統計学の知識を披瀝する部分は流暢だし興味深いものの、その他の部分については大根役者がセリフを棒読みしているようなぎこちなさが目立ち、世間が絶賛するほどのリーダビリティを感じることは出来ませんでした。
その上、主人公のケインを始めとする登場人物の造形も、表層的というか人となりに一貫性が無く、それぞれの人物の行動様式に説得力が欠けるチグハグな印象ばかりが残り、その面でもあまり感心出来ませんでした。そもそも、いくら癲癇(またATOKは、こーゆー政治的に正しくない単語を辞書に載せないんだから)が原因でまともな職に就けないからと言って、典型的なダメギャンブラー思考で窮地に陥る輩に感情移入しろというのが無理。
ユングの集合的無意識の存在を量子力学で説明し、そこを一歩推し進めて時間を超越出来る世界へのアクセスが予知を可能にするという、エンディミオン2部作の<虚空界>とも通じるSF的アイディア(ただし、癲癇や統合失調症といった精神疾患、あるいは人間の天才性を全てそれで説明しようとするのはやりすぎ)をアクションスリラーと絡めて描こうとした意気や良しとは思いますが、いかんせん技能がおっついていないという、大変残念感の残る作品でした。
超能力や超自然的な力といったありえない事象を、ウソに目を向けさせないように読者を話に引き込んでしまうキングやクーンツの文才というかテクニックは並じゃないのだな、と再認識しました。
|
|
マイノリティ・リポート
THE MINORITY REPORT, JAMES P. CROW, THE TROUBLE WITH BUBBLES, WATERSPIDER, STABILITY, THE CRYSTAL CRYPT, WE CAN REMEMBER IT FOR YOU WHOLESALES
フィリップ・K・ディック:著
朝倉久志:訳
早川書房:刊

|
殺人などの重大な犯罪を犯す者を「プレゴグ」と呼ばれる予知能力者が予見し、その情報をもとに犯罪候補者を逮捕することで重犯罪を一層した未来社会。そのシステムを築いた犯罪予防局のジョン・A・アンダートンは、将来的に自分の地位を継ぐであろう若き補佐役のエド・ウィットワーの就任を嫉妬混じりに迎える。ウィットワーにシステムの実際を見せるためプレコグのもとに案内したアンダートンは、プレゴクが予知した犯罪者名が記されたカードの中に自分の名前を見つけてしまう。
被害者の名前はアンダートンの全く知らない人物のものだったが、カードが自分を陥れるために捏造されたもので、自分の地位を手に入れようとするウィットワーと内部の協力者の存在を確信したアンダートンは逃亡を図るが、彼が殺すことになっている元軍人のレオポルド・カプランの手先によって拉致されてしまう…。(「マイノリティ・リポート」他6篇)
* * * * *
ポール・ヴァーホーヴェン監督の『トータル・リコール』の原作である「追憶売ります」、スティーヴン・スピルバーグ監督の『マイノリティ・リポート』原作の同名短編を含んだ、ディックの中・短編集です(日本オリジナル編纂の短編集なので、原本のタイトルが無いため原題欄が大変なことに(^_^;))。
映画化されたほとんどのディックの作品が、基本的な設定やプロットだけ利用して大胆にアレンジされてしまうことが間接的に証明(個々のアレンジが妥当かどうかは別として)しているように、ディックの作品には、どうもエンターテイメント性というかサーヴィス精神に欠けているとでも言いますか、本作の各話も「もっと膨らませればすっごい面白い長編になりそうなのに…」という食い足らなさというかもったいない感(悪く言うと「アイディアは面白いけど、それだけ」)ばかりが個人的には残りました。
具体的には、人間とロボットの支配関係が逆転している社会を描いた「ジェイムズ・P・クロウ」や、入れ子構造の宇宙観を導入して人間の驕りを批判する「世界をわが手に」なんて、もっとミステリィ仕立てにすれば、オチでもっと強烈な印象を残す怖い話になりそうだし、現代のSF作家を予知能力者だったと思いこんだ未来人が、自分たちが抱えた技術上の問題を解決するためにポール・アンダースンをSF大会から誘拐する、なんてプロットが楽しい「水蜘蛛計画」にしても、映画の『ギャラクシー・クエスト』ばりに突き抜けてハチャメチャなハナシにしても良さそうなものなのに、総じて文体も含めて筆致が淡泊なため、どうもメリハリに乏しい印象が。改めて『トータル・リコール』にしても『マイノリティ・リポート』にしても、原作のSF的仕掛けやエッセンスこそスポイルされてしまっているものの、娯楽作品のストーリィとしては上手く肉付けしたもんだなぁと感心してしまいました。
名作と言われる『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』すらピンと来なかったところを見ると、どうやらはるまきにはディックを理解する素養が無いようです。
|
|
星を継ぐもの
INTHERT THE STARS
ジェイムズ・P・ホーガン:著
池 央耿:訳
東京創元社:刊

|
ニュートリノ・ビームを利用して物体の非破壊検査を可能にしたトライマグニスコープを発明したヴィクター・ハント博士は、博士が勤めるイギリスのメタダイン・ニュークリオニック・インストゥルメント社の親会社IDCCから、突如すべての研究を棚上げにして、トライマグニスコープの1号機と共にアメリカの本社に向かうよう請われる。量産化を目前に1号機を貸し出すことは、社に壊滅的な打撃を与えかねない無体な要求だけに、ハント博士は訝しみつつも同僚と共に本社のあるポートランドに向かう。
ところがハントを迎えたIDCCの社長フェリクス・ボーランも、世界的な宇宙開発の計画立案・運用をつかさどるUNSA(国連宇宙軍)から極秘計画に利用するためにスコープを借り受けたいということ以外詳細は何一つ知らされておらず、ハントはすぐさまヒューストンへと飛ぶことになる。
ハントを待ち受けていたUNSAの航行通信局本部長グレッグ・コールドウェルは、3週間ほど前、月面の峡谷に穿たれた人口のものと思しき洞窟の中で、宇宙服を着た身元不明の遺体を発見したことを明かす。しかも地球に運んだ死体を詳細に調査をしたところ、“チャーリー”と名付けられた人物は5万年以上前に死んだことが明らかになったという…。
* * * * *
ハードSF界の旗手として名高いジェイムズ・P・ホーガンのデビュウ作です。
「人類より遙かに高度な文明が過去に存在した!?」というIfや、「ネアンデルタール人と人類を繋ぐミッシングリンクに迫る」という定番プロットは、一歩間違えると『リンク』やら『ネアンデルタール』のような箸にも棒にも引っかからない似非SFに堕しかねないわけですが、さすがオールタイムベストに名を連ねる本作は、やはりひと味もふた味も違います。
一つ疑問が解けると新たな根深い問題が現れてしまう“ルナリアン”の謎に対し、証拠と傍証から仮設を導き出し、それらの仮設が事実を過不足無く説明出来るかによって悪い仮設を淘汰していくという科学的手法をきちんと用いてその壮絶な歴史をつまびらかにしていく過程を丹念に描いているため、まるで現実の考古学ドキュメントを読んでいるかのような知的興奮を味わえるとともに、ミステリィ的興奮も味わえる大変読み応えのある作品となっています。
また、ややアクロバティック過ぎではあるものの、数多のトンデモ理論よりは遙かに辻褄の合う壮大なミッシングリンク宇宙来歴説には、似非SFでは到底味わえない、SFならではのワンダーを感じることが出来、SFを読む醍醐味を十分に味わわせてくれること請け合いです。
デヴュウ作ということもあってか、朴訥な文章の堅さと登場人物の魅力の乏しさのせいでややとっつきづらい印象がありますが、壮絶な運命に翻弄されたルナリアンが辿りついた末路がつまびらかにされることで静かな感動を呼ぶラストシーンは、それらの欠点を補って余りある、SF属性のある方なら必見の一流のSFだと思います。
|
|
Last Modified 2007/2/10
|  |